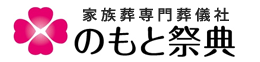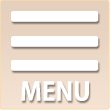最新ブログ記事一覧
- 価格競争はしません!
- 家族葬の長所と短所とは?
- 葬儀屋も見た目が大事!
- 宗教はなぜ存在するのか?
- 死去から葬儀までの日数
- 葬祭業をして良かったこと
- 離檀料ってあるの??
- 夏の葬儀で気を付ける点
- 葬儀への私の思い
- ご遺体用のドライアイス
- 2024年7月 (8)
- 2024年6月 (10)
- 2024年5月 (10)
- 2024年4月 (10)
- 2024年3月 (10)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (10)
- 2023年12月 (11)
- 2023年11月 (10)
- 2023年10月 (10)
- 2023年9月 (10)
- 2023年8月 (11)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 6月 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
納骨の時期とは?
こんにちは!
本日のブログは「納骨の時期とは?」と題して書かせていただきます。
実はご葬儀を終えた後にもご遺族は様々な手続きを行う必要があります。
例を挙げると年金の受給停止、運転免許証や健康保険証の返却、公共料金の名義変更、クレジットカードの解約、遺産相続、そして遺骨の納骨などですね。
その中でも今日は「遺骨の納骨」についてのお話になります。
日本は99.9%以上の方が火葬によって弔われる火葬国です。
よってご葬儀の後には遺骨がご遺族の手元に残ることになります。
では遺骨はいつまでにお墓に納骨をしなければいけないのでしょうか?
納骨の時期にルールはあるのでしょうか?
結論から申し上げると、遺骨はいつまでに納骨しなければいけないという決まりはありません。
極論ですが、半永久的に自宅に置いておいても法律には違反しません。
しかしながら、通常は日本の慣習に従って遺骨をお墓に納骨する方がほとんどであるというのが実際です。
そこで納骨をする時期なのですが、実は宗教によってその目安となる時期が異なります。
例えば仏教においては忌明けの四十九日(死後49日)、神道では忌明けの五十日(死後50日)を目安に納骨をする方が多いです。
もしも四十九日や五十日に納骨ができない場合は一周忌(死後1年)や三回忌(死後2年)などを目安に納骨をします。
ただし、これらはあくまでも目安であってルールや決まりではありません。
よってご遺族のお気持ちが安らいで来た時期を目安に納骨をするということでも全く構わないのです。
なお、キリスト教では納骨の時期に特に定めはありませんので、いつでも大丈夫です。
これから遺骨の納骨を予定されている方はぜひともご参考にしていただければ幸いです 😀
コメントをどうぞ
最新ブログ記事一覧
- 価格競争はしません!
- 家族葬の長所と短所とは?
- 葬儀屋も見た目が大事!
- 宗教はなぜ存在するのか?
- 死去から葬儀までの日数
- 葬祭業をして良かったこと
- 離檀料ってあるの??
- 夏の葬儀で気を付ける点
- 葬儀への私の思い
- ご遺体用のドライアイス
- 2024年7月 (8)
- 2024年6月 (10)
- 2024年5月 (10)
- 2024年4月 (10)
- 2024年3月 (10)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (10)
- 2023年12月 (11)
- 2023年11月 (10)
- 2023年10月 (10)
- 2023年9月 (10)
- 2023年8月 (11)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 6月 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||