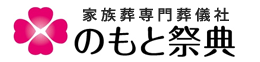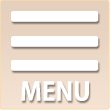最新ブログ記事一覧
- のもと祭典の目指す道
- 葬儀費用の目安とは?
- 家族葬の良い点とは?
- 1番多い葬儀の方法とは?
- のもと祭典の葬儀とは?
- 花まつりとは?
- 菩提寺が無い方へ
- 家族葬と一般葬の違い
- ご遺体に着せる服とは?
- エンバーミングが不要な遺体
- 2024年4月 (8)
- 2024年3月 (10)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (10)
- 2023年12月 (11)
- 2023年11月 (10)
- 2023年10月 (10)
- 2023年9月 (10)
- 2023年8月 (11)
- 2023年7月 (11)
- 2023年6月 (10)
- 2023年5月 (13)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 3月 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
骨壺の大きさ
おはようございます!
今日のブログは「骨壺の大きさ」について書かせていただきます。
まず「骨壺」とは何かと言うと、ご存知のようにご遺体を火葬した後にその焼骨を収めるための壺です。
ではその骨壺はどれくらいの大きさのものを使用するのでしょうか?
答えを申し上げると、骨壺の大きさは地域によって異なります。
東京などの東日本では直径が6寸~7寸(18㎝~21㎝)のサイズ、大阪などの西日本では直径が4寸~5寸((12㎝~15㎝)のサイズが主流です。
なぜ東日本と西日本で骨壺の大きさが異なるのかと言うと、それは焼骨をどの程度まで骨壺に収めるのかという話に繋がります。
一般的に東日本では「全部収骨」と言って焼骨を全て骨壺に収めますが、西日本では「部分収骨」と言って焼骨の一部分しか骨壺に収めません。
そのような理由から東日本と西日本では使用する骨壺のサイズが異なるということになります。
ちなみに西日本では収骨しない分の焼骨はどうするのかと言うと、火葬場の職員によって後日まとめて寺院などの合葬墓に埋葬されるのだそうです。
最後に、焼骨をメインの大きい骨壺と小さい骨壺に分ける場合(※分骨をする場合)は、小さい分骨用の骨壺は直径が2寸~3寸(6㎝~9㎝)のものを使う場合が多いです。
ご参考にしていただければ幸いです 😉
コメントをどうぞ
最新ブログ記事一覧
- のもと祭典の目指す道
- 葬儀費用の目安とは?
- 家族葬の良い点とは?
- 1番多い葬儀の方法とは?
- のもと祭典の葬儀とは?
- 花まつりとは?
- 菩提寺が無い方へ
- 家族葬と一般葬の違い
- ご遺体に着せる服とは?
- エンバーミングが不要な遺体
- 2024年4月 (8)
- 2024年3月 (10)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (10)
- 2023年12月 (11)
- 2023年11月 (10)
- 2023年10月 (10)
- 2023年9月 (10)
- 2023年8月 (11)
- 2023年7月 (11)
- 2023年6月 (10)
- 2023年5月 (13)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 3月 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||